
採用情報
北海道の蔵元として
北海道はほかのどの地域よりもすばらしい海と畑の産物に恵まれています。
私たちはこの自然の恵みを大切に、醤油・味噌の食品づくりを通し、北海道の食卓を豊かにすることを使命としてきました。私たちは令和3年(2021年)に創業130周年を迎えます。これまで幾度となく、経済や社会の変化に直面してきました。そんな中、私たちは伝統を重んじ、独自の製造技術を守りながら、北海道のおいしさを皆さまの食卓にお届けしてきました。
「おいしく安全な食品」を通して、消費者の皆さまと信頼関係を築き上げられたからこそ、企業活動を続けて来られたと考えています。私たちはこれからも皆さまとの信頼関係を礎とし、和食の素晴らしさを未来へ継承していきます。
「北海道の蔵元」として、北海道素材のおいしい食品を皆さまの食卓へお届けすること。食生活の向上、ひいては、地域経済の発展に貢献していきたいと思います。
福山醸造株式会社 代表取締役社長
福山 耕司KOJI FUKUYAMA

社員の声

「家庭の味」をつないでいくこと
福山醸造株式会社
家庭用事業部 北海道エリア 課長代理
林 和樹KAZUKI HAYASHI
家庭用事業部はスーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、アンテナショップ等多岐に渡って自社商品を中心に販売を行う部署です。現在、同部署の課長代理を務める林和樹さんは、入社から10年以上、業務用事業部に所属していました。
「業務用事業部では主に飲食店やホテル、工場等を担当し、自社商品の販売を行うことはもちろん、お客様のオリジナル商品の開発等にも携わっておりました。」
業務用商品は家庭用商品とは異なり、一般のお客様が直接目にする機会は少ないですが、普段何気なく口にしている食事や、販売されている商品の原材料として使用されていることも多く、多様化する食生活の中で《縁の下の力持ち》の役割を担っています。
一方で家庭用商品は、多くの販売チャネルで取り扱われているため、自社商品が並んでいる売場に遭遇することも珍しくありません。
「数ある商品の中からお客様が弊社の商品を手に取る姿を見ると、とてもありがたい気持ちになります。家庭用商品と業務用商品、どちらが欠けても当社は成り立ちませんし、日々の食卓を支えていくことはできません。両方の経験を通じて、お客様にとって魅力ある提案を発信していくことが、私の努めと自負しております。」

創業以来、たくさんのお客様に支えられながら、歴史を歩んできた福山醸造。メーカーとして代々継承されてきた伝統の味が、そのまま各家庭や取引先にも受け継がれていることを実感する場面も多いそうです。
「”トモエの商品でなければ、うちの味にならない。”そのような声を家庭用、業務用、どちらのお客様からもいただいたことがあります。世代を超えて伝えられていく味に《トモエ》が脈々と刻まれていく。自社の歴史のみにあらず、そういったお客様の想いも背負っている。それらのことを肝に銘じて、日ごろから《トモエ》の名に恥じぬよう、日々の業務に取り組んでいます。」
伝統は守るものではなくつなぐもの。先人達から次世代へ受け継がれていくものと、多様に変化していく時代に順応し、進化しながら攻めていくもの、その両面がこれから先の時代において不可欠となっていくことを感じています。
「我々営業はただ商品を売って届けるのでは無く、皆様の家庭の味も一緒にお届けしています、歴史のある業界において、柔軟な姿勢を持ってこの先の時代にお客様と共に歩んでいきたいと思っております。」

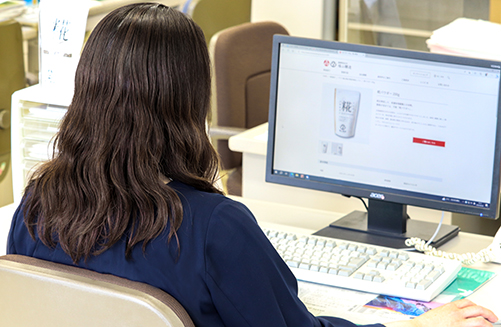
伝統とチャレンジ精神をつなぐ
「ヤマト福山商店」
福山醸造株式会社
ヘルス&ビューティ事業部 H&B販売課 課長
阿部 幸代YUKIYO ABE
120年を超える福山醸造の長い歴史の中で、大きな転機となる「ヘルス&ビューティ部門」が新設されたのは2019年5月。別会社で商品開発をしていましたが、自身が手がけていた商品権利を福山醸造へ譲渡するのと合わせ、同社に入社しました。
福山醸造で新たに販売することになったのは、「まるごとピューレ北海道」、「ドライパック」「北海道のこだわりプリン」、「北海道のなめらか羊羹」 、「北海道あまざけ」の5種。いずれも北海道産の素材を使用し、『からだに優しい』をコンセプトに開発されたものです。なかでも「北海道あまざけ」は、福山醸造の米糀を使用したもので、同社をつなげるきっかけになった商品です。
現在、ヘルス&ビューティ部門で活躍するのは3名の女性陣。福山醸造の主力であるトモエブランドと並ぶ新ブランドの立ち上げに向け、奔走中です。「福山醸造に入社して、まず最初に驚いたのが同社の長い歴史でした。開拓まもない札幌から今に続く歴史の重みに、ひたすら圧倒されました。」電気が灯りはじめた開拓期の札幌で、福井県から北海道に移り醤油造りを始めた先人たちの不屈の精神に身が引き締まる思いだったと言います。
福山醸造の歴史に心を動かされた阿部さんは、その思いを新ブランドのネーミングに落とし込むことを決めました。福山醸造の原料を使い、他社とタッグを組み、別工場で製造する−−。
これまで自社工場で製造したものを販売していた福山醸造にとって、「新ブランド」は同社の長い歴史において大きな革新です。

伝統と革新。福山醸造の新たな章のスタートにふさわしいと考えた新ブランド名は「ヤマト福山商店」。福山醸造の創業当時の社名を、あえて新ブランド名に選んだのです。「ヤマト福山商店は、福山醸造にとって新しい挑戦です。だからこそ、開拓の地で商いに挑戦した先人の意思を引き継ぎたいと思ったんです。先人たちが切り拓いた歴史の上に、いま私たちが立っているということを大切にしたいと考え、あえて原点でもあるヤマト福山商店という名前に決めました。」老舗企業の安心と信頼、先人から今につながる福山醸造のチャレンジ精神が、この新ブランド「ヤマト福山商店」には込められています。
ヤマト福山商店の新商品開発にあたり、注目しているのが福山醸造の「米糀」です。米糀のプロフェッショナルである福山醸造だからこそ可能にする、米糀を使用した新商品のリリースを目指し日々研究を進めています。「福山醸造の新ブランドにふさわしい商品にしなくては、とプレッシャーもあります。」現在開発中の「糀パウダー」は、夢の実現の第一歩です。「手軽に甘酒をつくったり、味噌汁に加えたり、ヨーグルトに混ぜ合わせるなど、米糀に注目が集まる今、皆さんがより手軽に米糀を利用できるよう考えた商品です。」米糀のポテンシャルを最大限に引き出したいと考え、化粧品開発も視野に入れています。
『糀で実現する健康と、キレイ』を目指し、「自社オリジナルの米糀もいずれ開発したいです。」


手間暇を惜しまず、
各家庭に馴染むお醤油を
北海道醤油株式会社(製造工場)
製造管理部 品質管理課 課長
霜野 太虹TAIKOU SHIMONO
2011年に入社した霜野太虹さんが勤める苗穂の醤油工場は、大正7年に設立。その後、高度経済成長を経て、大量生産が可能な設備が整えられましたが、一方で、全く変わらないものもある、と霜野さんは話します。
「作業時間の短縮が必然とされる中であっても、レンガ蔵で6ヶ月以上ゆっくりと時間をかけてもろみを発酵させています。ゆったりと流れる時間が美味しいもろみを育て上げるというのは、今も昔も変わらない工程です。」醤油の醸造は非常に繊細な作業。小さな変化も、味や品質に大きく関わってきます。「もろみ作り一つとっても、人の手を介しての作業は必要です。どれだけ機械化が進んでも、人の経験や勘が結局は生かされるのです。それが醤油づくりの難しさであり、面白さですよね。」と霜野さんは胸を張ります。福山醸造が長く愛される理由は「古いものを大切にすることと、新しいものを取り入れることのバランス感覚」にあると、霜野さんは語ります。「先輩社員から聞いた話なのですが、お味噌を袋に詰めて販売したのは当社が北海道初だったそうです。カップに入れたのも北海道内で二番目、醤油をペットボトルに入れたのも比較的早かったと聞いています。福山醸造は新しくて良いものを積極的に取り入れる会社なんですよ。」

容器の変更は工場の設備や工程にも大きく関わることです。「時代に合った容器を模索し、積極的に取り入れる姿勢も、そのひとつなんです。」と霜野さん。「これからの日本はさらに少子高齢化が進み、人口も少なくなり、家族構成も変わっていきます。少し前までは1Lの醤油が主流でしたが、使い切れないという声をよく聞くようになりました。最後まで使い切ることのできる小ぶりな容器や、空気に触れず、長く鮮度が保てる容器など、各家庭の食卓に馴染み、そして愛されるものを追求しています。」
入社当初よりも、商品数はさらに増え、工場の作業はより複雑化しています。「それでも手間暇を惜しまずお客様のニーズを追求し、食卓に貢献することが、北海道では老舗と呼ばれる福山醸造の存在意義だと思い、日々醤油づくりを行っています。」
